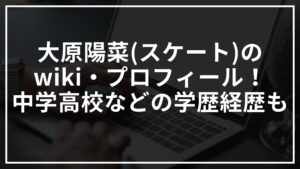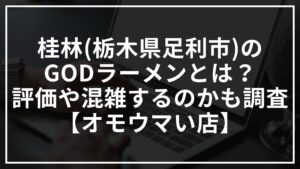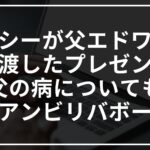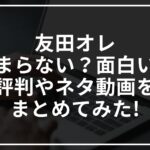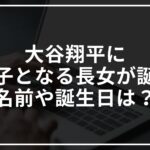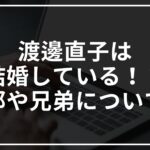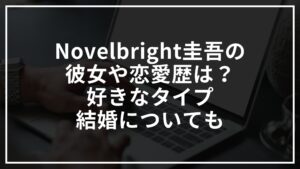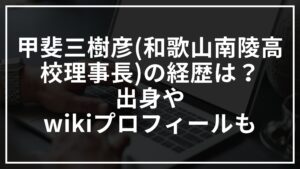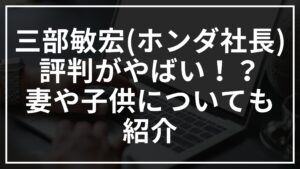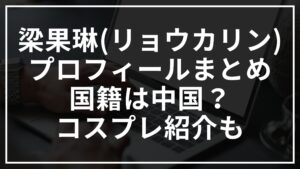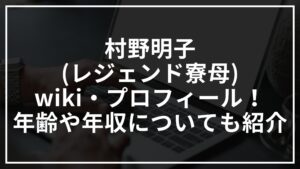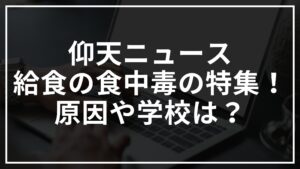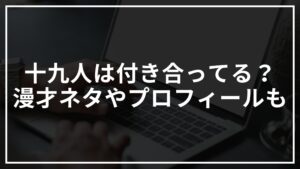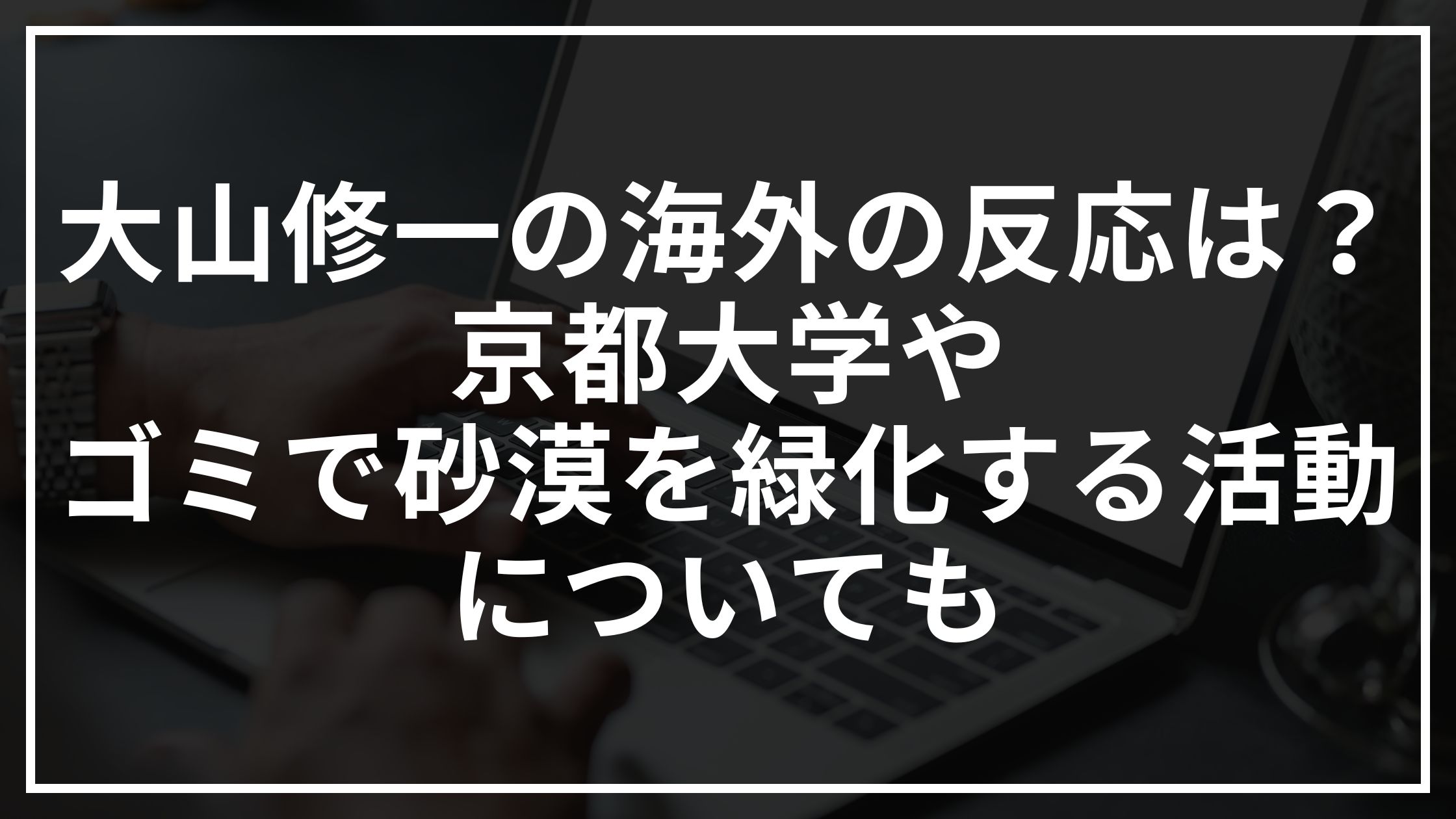
今、世界中で深刻になっている砂漠化の問題。
でも、なんとゴミを使って緑を増やすという、
すごく画期的な取り組みが注目を集めているんです。
その取り組みを進めているのが、京都大学の大山修一教授です。
2025年1月13日の激レアさんを連れてきた。にも出演されるなど、今とても注目されている教授の方です。
この記事では、
大山修一教授の海外の評価や京都大学での活動、
中心となって進めている「ゴミを利用した砂漠緑化プロジェクト」について、詳しくご紹介します。
大山修一教授の海外の反応
世界中から注目される大山修一教授の取り組み
大山修一教授のプロジェクト、
実は海外からもすごく評価が高く注目されているようです。
特に海外から注目されているのが、
「環境を守りながら、その地域の人々の暮らしも良くしていく」というアプローチ。
後にくわしく解説しますが、
ゴミを使って砂漠を緑にするで、環境も良くしつつその地域暮らしも改善する活動を行っています。
その活動に、国連をはじめ世界中のNGO団体が興味を持っているんです。
例えば、このプロジェクトのいいところは、
お金があまりかからないうえに、その土地にあるものを上手く使っているところ。
だから「他の発展途上国でも、まねできそう!」って評価されているんです。
さらに、世界中の研究者が集まる国際学術会議でも、
「環境と社会をつなぐ素晴らしい実例」として、
どんどん取り上げられるようになってきています。
これからの展開と期待される効果
大山教授は、このプロジェクトをもっともっと広げていこうと考えています。
具体的には、ニジェールだけでなくサヘル地帯全体や、他の乾燥した地域にも広めていく計画なんです。
特に力を入れているのが、
それぞれの地域の特徴に合わせて土を改良する技術を応用することと、現地の人々ともっと協力関係を深めていくことです。
さらに面白いのが、最新技術も取り入れようとしているところ。
AIやドローンを使って緑化した場所を観察したり、
肥料を効率よく与えたりする方法を考えているんです。
このプロジェクトが世界中に広がれば、
地球全体の砂漠化対策のお手本になるかもしれません。
大山修一教授の京都大学での研究活動について
京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科でどんな研究をしているの?
大山修一教授は、京都大学のアジア・アフリカ地域研究研究科で研究をしています。
主に、アフリカの村々で起きている様々な変化について調べているんです。
例えば、昔ながらの自給自足の生活から、
お金を使う経済に変わっていく様子や、
土地を使うルールがどう変化しているのかなどを研究しています。
村の人たちが直面している問題を深く研究して、
これからも村で暮らす人々が豊かに生活できる方法や、
環境問題を解決する方法を探っているんです。
アフリカの村々での現地調査を重視する研究スタイルについて
大山教授は、
ザンビアやニジェールといったアフリカの国々で、長い間、現地調査を続けてきました。
京都大学では、現地調査を重要視するスタイルで研究が行われているそうです。
「フィールドワークを重んじる、徹底した経験主義ですね。ゼミの発表などでも、『それは現地で見てきたのか?』というようなツッコミがよく入ります。その人が実際に『見た』と言えばみんな納得する。それというのも、京都大学の人類学の先駆けとなった霊長類研究では、緻密な観察によって個体を識別したり、群れでの順位付けや性格といった個性を把握したりしてきました。そうした姿勢が地域研究にも引き継がれているんだと思います。
村に住む人々が自然をどう見ているのか、自然の恵みをどう使っているのか、村の人々がどうやって助け合って生活しているのかなど、いろいろな角度から調べています。
特に力を入れているのが、ニジェールのサヘル地帯での活動です。
ここでは、砂漠化や貧困、争いごとなど、いくつもの問題が重なり合って起きています。
そこで、現地の人々と一緒になって、これらの問題を解決する方法を探っているんです。
大山修一教授のゴミを使って砂漠を緑にするプロジェクトとは?
そもそもサヘル地帯の砂漠化とは?ニジェールの状況について
サヘル地帯は、大きなサハラ砂漠のすぐ南側にある地域なんです。
ここでは、雨が降らない日が続いたり、気候変動の影響で、近年どんどん砂漠化が進んでいます。
特にニジェールでは、1970年代から砂漠化が深刻になってきて、
作物が育ちにくくなったり、食べ物が足りなくなったり、貧困が広がったりと、いろんな問題が起きているんです。
そして、さらに困ったことに、
都市に人が集まってくるようになって、
ゴミが増えたり、街の衛生状態が悪くなったりする問題も出てきています。
都市と村の間で、物が上手く循環していないことで起きる問題
ニジェールでは、村から都市に野菜や穀物を送る一方で、
都市で出るゴミや生ごみが村に戻っていかないんです。
その結果、村の土地は栄養不足になって、作物が育ちにくくなっています。
反対に、都市ではゴミが溜まって衛生状態が悪くなり、
病気が広がりやすくなっているんです。
こうした問題は、環境だけでなく、社会や経済にも大きな影響を与えています。
家庭から出るゴミで、土を豊かにする方法
大山教授のプロジェクトでは、
都市で出る家庭ゴミを集めて、村の荒れた土地に運んでいます。
そのゴミを土に混ぜ込んで、上から砂をかけることで、
土を栄養たっぷりにする方法を取り入れているんです!
こうすることで、ゴミの中の生ごみが分解されて、土が肥える仕組みです。
面白いことに、ビニールなども役立っていて、
土の水分が蒸発するのを防いで、植物が育ちやすくしているんです。
緑が増えることで、村の人々の暮らしはどう変わった?
このプロジェクトには、たくさんの良い効果が出ています
- 作物がよく育つようになって、食べ物不足の問題が解決に向かっています。
- 家畜の餌となる草も育つようになり、牛や羊を育てる仕事も安定してきました。
- 農業をする人と、家畜を育てる人の間でトラブルが減って、村の雰囲気が良くなっています。
- 新しい仕事も生まれるので、村の人々が自立した生活を送れるようになってきているそうです。
このように、環境が良くなるだけでなく、
村全体の暮らしが豊かになっていっているんです!!
まとめ
大山修一教授が取り組んでいる「ゴミを利用した砂漠緑化プロジェクト」、
実はすごくユニークで素晴らしい取り組みですよね!
環境を守りながら、同時に地域の人々が抱える問題も解決していっており、
まさに一石二鳥という感じがします笑
これからもっとプロジェクトが広がっていけば、
他の地域でも同じような取り組みが始まって、
地球全体の環境を良くすることにつながっていくかもしれませんね